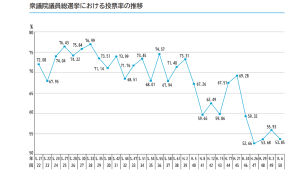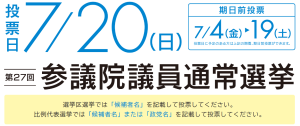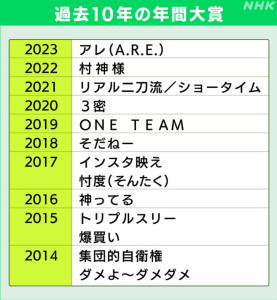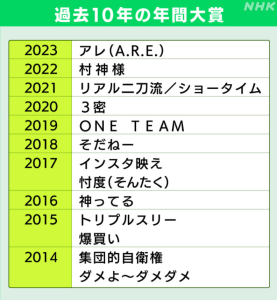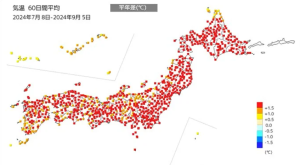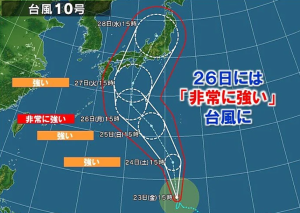国際化と国際人の育成(4)(25)
今回は私の幼い頃の思い出と、上海の生家訪問にまつわる話しについて記したいと思います。
私の外国との最初の関わりは、1942年(昭和17年)10月に中国・上海市で生まれたことから始まります。出生地は上海市虹橋区という日本租界の中でした。父は当時、日本の貿易会社の駐在員で在上海日本国領事館に出生届を提出し、後日、本籍地である広島県広島市長受理と記載されています。その頃のことは今となっては父に確かめることもできず、記憶も残っていません。ただ私が生まれて間もなく母が亡くなったため、末っ子の私を含め乳幼子3人を連れ、父は間もなく帰国したようです。
終戦時(1945年8月15日)は兵庫県・芦屋市に住んでいました。記録によると芦屋は同年6月から計4回空襲されました。特に、終戦直前の8月5~6日は「阪神大空襲」として歴史に残るほど激しかったようで、市街地を目標として1500発の焼夷弾が投下され、一面焼け野原になり多数の死傷者が出たそうです。当時私は3歳目前でしたが、脳裡には父親の背中に背負われ、畑の中を逃げたその一瞬だけが夢・幻の如く残っています。当然のことながら私たち家族が住んでいた家も焼き払われ、家財をはじめすべてを失いました。後に、育ての母は「茶碗一つ、箸一本からの再スタートだった」と言っていました。なお、私が今日あるは、今は亡き「育ての母のおかげ」と、常に感謝しています。
こういった戦争中の過酷な経験については、全くと言っていいほど記憶はありませんが、今も思い出すのは戦後の食糧難でした。ともかく「餓鬼」と称される食い盛りの時に食べるものがない。空腹を我慢するのは今も思い出すほど辛いことでした。親は本当に苦労したと思います。これは私だけでなく当時のほとんどの子供は同じ境遇だったと思います。その功名として私は好き嫌いが全くありません。まさに味覚が育まれる時期が、選り好みを許されない時代だったからです。それで今も「甘すぎる・辛すぎる」くらいの区別はつきますが、デリケートな味の違いへの感覚は鈍く、何であれ「土佐の皿鉢料理」のように目の前にドンとあると、本能的にうれしくなるのです。「三つ子の魂百まで」と言いますが、「いつでも食べ物がある訳ではない」という幼児体験が、「量があるだけで幸せ」という思いに結びついているのだと思います。
因みに太平洋戦争は約3年8カ月続き、300万人を超える日本人が犠牲になりました。私は物心がついた程度の年頃で、実際には親の世代が大変な目にあったのですが、いつ何時、空から爆弾が落ちてくるかわからない恐ろしさや、終戦直後の食糧不足を振り返ると、今のコロナ感染による日常生活の不自由さくらいは、私は十分我慢できる範囲内と受け止めています。
なお、私が出生時は別にして、中国を最初に訪れたのは1976年11月です。その後数十回訪中しましたが、1986年5月に初めて上海の生家を訪れました。中国の知人が案内してくれたのです。中国では1979年から改革開放政策の下、建設ラッシュとなりましたが、上海は開発が遅れていたことから生家はそのまま残っていました。そして家の前をうろうろしていましたら、当時の住人Aさんが家の中に招じ入れてくれ、にわか「日中友好」となりました。Aさんはそれなりの社会的地位にある人物でした。そういった縁でAさんとの文通が始まりました。
一方、当時の中国の生活環境は厳しく、国民の間ではよりよい生活、職業を目指し、先進国・日本への留学熱が極めて高い状況でした。今でこそ中国人留学生は約12.2万人 (昨年5月1日現在) に達していますが、当時は日本政府の認可を得るには日本での身受け保証人が必要でした。私はAさんから懇請され身内とされる2人を引き受けました。ところがその後も依頼があり、私は子供の明るい将来を願う親の気持ちは理解したものの、別の「意図」を感じ、一方的に文通を打ち切らざるを得ませんでした。誠に残念でしたが、今となっては苦くも懐かしい思い出です。