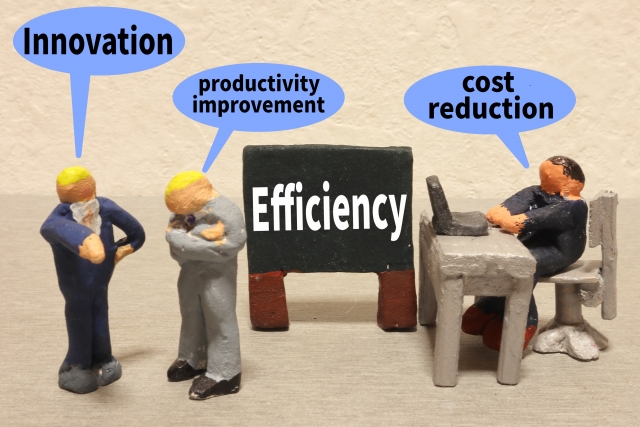米国でのくらしとビジネスを振り返って(3)(35)
私が1978年6月に赴任した当時の米国社会は非常に荒廃し、ニューヨークは殺人件数が全米一の危険な街でした。マンハッタンの中心部でさえ、暗くなってからは一人では歩かぬよう、また角を曲がるときは出会いがしらの犯罪を避けるため、大きく回るよう忠告されたほどでした。実際に犯罪に会った日本人駐在員も何人かいました。
この治安の悪さの背景には、10年続いたベトナム戦争(1975年4月1日終結)の後遺症が指摘されます。約5.8万人の戦死者を出した挙句、南ベトナム政府の崩壊により米軍は撤退しました。ベトナム戦争の暗部は映画「プラトーン」にも描かれています。結果として「大義なき戦い」となり、激しい反戦運動の中、ベトナム帰還兵は国民から歓迎されることもなく、職は見つからず心はすさみ犯罪に走ることになったのです。
さて、現在のニューヨーク市の人口は約840万人、人種構成は白人が33%、ヒスパニック系(スペイン語圏出身)が29%、黒人が23%、アジア系が13%です。アジア系で多いのは中国人でマンハッタンにはチャイナタウンがあります。日本人は5万人以下(1%以下)です。私が在住した頃はもっと少数でした。2歳の時ニーヨークに渡米した私の娘が3年後、日本に一時帰国した際、家内に「Mama, Why so many Japanese, here!」と尋ねたそうです。平素、人種のるつぼの中にいる娘の目には不思議に映ったのでしょう。一方、我々日本人もマンハッタンを歩いていると、現地人から道を尋ねられたことが何度もありました。誰でも米国にいれば同じ米国人という感覚なのです。
ニューヨークのニックネームは「ビッグ・アップル」。その由来には諸説があります。わたし流の解釈は「かじり甲斐のある街」です。ニューヨークには美術館、オペラハウス、それに自然博物館、植物園、マンハッタンのど真ん中にはセントラルパークがあります。そして有名なカーネギーホールや、ブロードウェイの劇場。私は武骨なタイプで、最初は首に縄をつけられたようにミュージカルに連れていかれましたが、だんだんとはまってしまいました。ニューヨークは本当に魅力溢れるエキサイティングな街です。
食事はもちろんステーキが主ですが、おすすめはイタリア料理。ダウンタウンにはリトル・イタリーがあり、ゴッドファーザーの世界に思いを馳せながら飲むワインは最高でした。ワインといえば、ある時、そこそこのレストランで、「この料理には白か赤か」とソムリエに尋ねたところ、「アンタが金を払うんだから好きな方を飲めばいいじゃないの」という答え。フランスではこうはいきません。米国人は基本は基本として、最後は個人の自由といったような風です。この気取らない「ざっくばらん」なところが私は好きです。
それと日本にはなく米国にあるのがチップ制度です。チップをどんな時に、どれくらい払うか分かるようになれば駐在員として一人前です。米国では接客サービス業の人たちの固定給部分は安く、チップが個人の収入に占めるウエイトが高いのです。だから少しでも多くチップをもらうため頑張る、それがサービスの質と生産性の向上につながるという点で合理的です。一方、チップ制はありませんが、日本人労働者のサ―ビス精神(おもてなし)は外国人から賞賛されます。しかし労働生産性は米国の30~40%の水準に止まるとされています。その裏には労働力余剰時代の名残りと、我が国の就業者全体の約7割を占めるサービス産業の、過当競争体質→過剰サービス→労働生産性の低さ、という構図が存在するように思います。
今後我が国では労働力不足が一段と進み、業種間・企業間で人材の奪い合いとなります。以前はタダと思われていた「水と安全(保障)」は、今やそうではないことは国民的常識となっています。これら二つに加え、「サービス」も有料という方向に、発想を転換していかなければならないように思います。