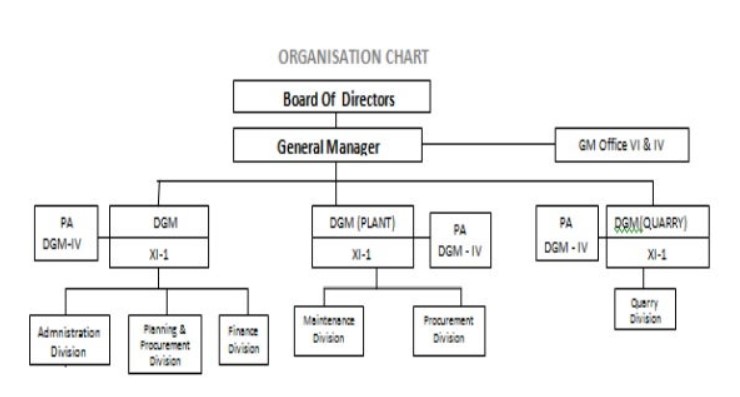「人を育てることの大切さ」(2)~ 人への投資が大事 ~(47)
政府の経済財政運営や来年度予算案の基本となる、今年の通称「骨太の方針」(経済財政運営と改革の基本方針)が6月7日に閣議決定されました。その柱の一つとして、岸田首相が掲げる「人への投資」に重点を置くとして、3年間に4000億円投じることが盛り込まれました。なお、「人への投資」を採り上げたのは今回が初めてのことです。
我が国は伝統的に「モノづくり国家」を標榜してきました。そして製造業は1億2千万人を擁する国内市場でのマーケット・シェアの拡大を目指し、ひたすら他社に負けない「高品質・高機能」なものを造るという思想が根強く、投資の重点はもっぱら、”Hard”に置かれ、「人材育成」といった”Soft”への投資は二の次とされてきました。
因みに、日本の製造業は海外市場でも同じ戦略、つまり品質と機能さえよければ売れるという一方的な考えで進めました。一方、韓国、中国のメーカーは徹底的に現地市場を調査・研究し、多機能よりも現地のニーズ(好み・慣習・生活水準)に合う製品を、しかも安く売り込みました。その結果、日本のメーカーは家電、携帯電話など新興国でマーケット・シェアを大きく失ったのは周知のとおりです。
以上のように、日本は国も企業も技術開発に重点を置き、「国際的に活躍できる人材」、並びに「マネジメント能力のある人材」の育成、つまり「人への投資」を怠ってきました。そのため民間部門だけでなく、政府・公的機関でも国際的に通用する人材が不足し、世界における我が国の存在感の低下をもたらす一因となっています。
経営資源として「ヒト・モノ・カネ」と言われますが、最近はこれに「情報・技術」というSoft力が加わります。これらの中で「ヒト」、つまり「人材」が大事なことは古今東西言われているところです。例えば中国の古典・管子の中に「100年先を考えるなら人を育てよ」という教えがあります。孟子の言行録にも「天の時、地の利、人の和」、そして我が国でも、戦国の武将・武田信玄公は「人は城、人は石垣、人は堀、情けは味方、仇は敵なり」と詠んでいます。
また、私が尊敬する人物の一人である、山本五十六・元元帥海軍大将は、人材の育成に必要なこととして「やってみて、言って聞かせて、させてみて、ほめてやらねば、人は動かじ」、そして更に「やっている、姿を感謝で見守って、信頼せねば、人は実らず」という言葉を残しています。つまり人材の育成には「率先垂範・忍耐と寛容・感謝・思いやり」が必要ということです。
因みにもう一つ、同元帥は「忍耐」の大切さについて、「男の修行」の中で「苦しいこともあるだろう、言いたいこともあるだろう、不満なこともあるだろう、腹の立つこともあるたろう、泣きたいこともあるだろう、これらをじっとこらえていくのが、男の修行である」と諭しています。
私は同元帥の足元にも及びませんが、モットーとしてきたことは「他人(ひと)が出来ることは他人に任せ、自分は他人が出来ないことにチャレンジすること」です。そうすれば人は育ち、そして自分も成長し、結果として組織は活性化し、業績も伸びると考えるからです。
どういう組織であれ、それぞれが地位と役職にふさわしい仕事の「質」が求められるのは当然です。そういった側面から今や我が国企業においても、伝統的な「メンバーシップ型」(終身雇用型)から、「ジョブ型」(職能型)への移行が増加しつつあります。
《追記》以前から資源価格は様々な理由で上昇傾向にありましたが、ロシアのウクライナ侵攻が加わり、石油、天然ガス、石炭といったエネルギー関係に止まらず、肥料、小麦を中心とした穀物、飼料等、広範囲に物価上昇の波が世界的に押し寄せ、インフレーションの加速が懸念されています。インフレがなぜ怖いかというと、現金や預貯金などの価値が目減りして生活を脅かすからです。緩やかな物価上昇は経済成長も促しますが、激化すると簡単には収まりません。我が国でも広範囲にわたる消費財に値上げの動きが出ています。中でも政策的に価格が低く抑えられている電気は、供給量の確保とともに今後の上昇が気になります。
米国は既に金利引き上げに転じ、EUもまもなく金融引き締めに向かうようです。そのため世界銀行はこのほど、2022年の世界全体の成長率を2.2%とし、前回(1月時点)から1.2ポイント下方修正しました。同時にスタグフレーション(物価上昇の中で景気が後退する)のリスクなど、今後の景気動向への懸念を示しています。