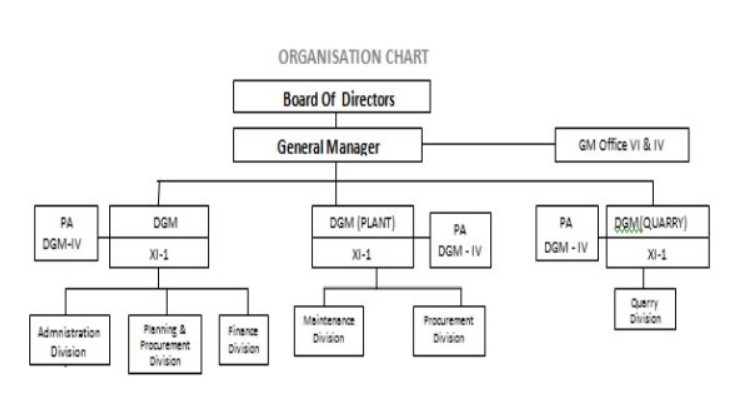「人を育てることの大切さ」(4)~組織について~(49)
前号で記した通り、「組織」そのものは「木で彫った仏像」というか、単なる「骨格」にすぎません。従って大事なのは「木の仏像」にどのように血液を流し込み、魂を入れるかであり、その決め手になるのが「人事」です。
なお、組織を改定したからといって、「ひと」をすべて入れ替えるわけではありません。外部からの人材の登用・補充も必要ですが、多くの場合、現有の人材の再編成が中心となります。従って経営トップは組織改定とそれに伴う人事について、その趣旨・目的を明確にすることが必須です。さもなければせっかくの組織改定も効力を発揮することなく、気分転換のようなことに止まります。私は組織改定・人事の最大の目的は社員の「意識改革」にあると考えます。正に社長が社員に送るメッセージです。そこから社員はいろいろ読み取るのです。
強い組織というのは、いうなれば炊く前の「米粒」のように一つ一つバラバラではなく、「餅」のような融合体です。一つの企業理念を共有することと多様性(ダイバーシティ)は矛盾するものではありません。多様性は共有する企業理念をより効率よく、効果的に実現するために必要な要素です。なお、「米国の組織は戦略に基づき、日本の組織は流行に従う」と揶揄されますが、日本企業は横並び、先例主義が未だ主流です。その方が無難だからです。組織体制を考えるに当たっては、トップの明確な事業戦略が不可欠です。
どんな組織形態を採り入れても必ず強いところ、弱いところがあります。将棋でもいろいろな陣形(いわば組織形態)があります。それぞれ一長一短があり、どれを選択するかは「積極的に攻める」か、「守りを固めるか」といった情勢判断によります。「必勝」とか「究極」の組織はないのです。また、組織とか制度というものは経年劣化(制度疲労)を生じるものです。ですから弊害を感じたら見直すことです。
なお、現状の組織については特に弱点に目が行くものです。ところが組織改定によりその点は改善出来ても、万事解決とはならず、また新たに想定していなかった問題が生じます。従って組織を構成する「ひと」がそれぞれの組織の弱点・欠点を自覚し、スキのない・強い組織を目指すにはどうすべきか、プラス・アルファの「目配り・気配り・心配り」をすることが大事です。野球でも名野手は非常に守備範囲が広いのです。
最近、物流業界の大手二社が対照的な組織再編を行い話題になりました。うち1社は事業部制からホールディング・カンパニーに移行し、もう一社はワン・カンパニーへと先祖返りしました。一社は「今後の国内外の環境の変化に臨機応変に対応する」、もう一社は「多角化路線から特定の事業分野に特化し、生業を深堀し基盤を盤石にする」という経営戦略に基づく再編成と考えます。
なお、私は前職在任中、組織の在り方について語るとき、常にスローガンとして掲げたのは「『明るく、楽しく、のびのびと、風通しのよい組織』を目指せ」という、単純明快な言い方でした。難しい組織論や語彙は学者の先生方や評論家にお任せし、経営者は社員の腑に落ちるように分かりやすく、そして粘り強く語ることが大切です。
追記:先日、スイスの有力ビジネススクールIMDが、2022年の世界競争ランキングを発表しました。調査対象は63カ国・地域で、各国政府や世界銀行の統計データと、経営者へのアンケート調査などをもとに集計しました。
それによると、デンマークが初めて首位となったほか、欧州勢が上位10カ国のうち6国を占めました。コロナ禍からの経済再開のスピードの速さと、デンマークの場合は行政のデジタル化が進み、生産性や事業効率化が他国より進んでいることが、トップに選ばれた理由としています。
アジア勢ではシンガポールが3位(前年は5位)、香港が5位(同7位)、台湾も7位に上がりました。一方、日本は順位を3つ下げ過去最低の34位となりました。「政府の効率性や国家の債務残高がGDPの2倍を超えていること」が指摘されています。
日本人は未だ「経済大国」という幻想に浸っているところがあります。このままでは「ゆでガエル」になります。一連の厳しい国際的な評価を直視し、「意識改革」を進め、政・官・財・民が足並みを揃え国力の再興を目指すことが必要です。さもなければ日本はいずれ間違いなく沈没します。