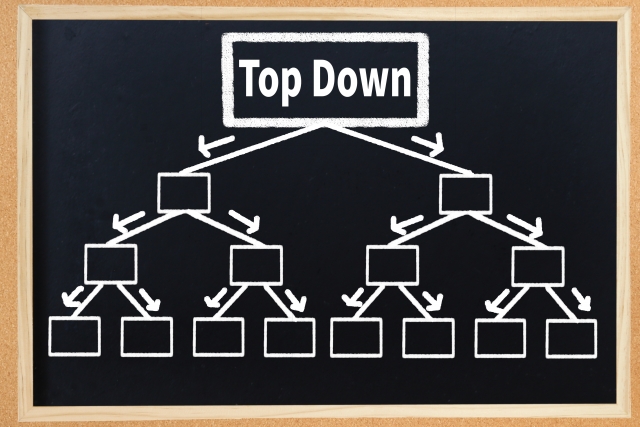「人を育てることの大切さ」(5)~組織について(その2)~(51)
今回は異なる組織の融合と、IT時代における組織の在り方について記します。
典型的なピラミッド型組織である軍隊は、通常、陸軍、海軍、空軍により構成されます。そして米国では三軍の作戦の指揮統一を図るため設置されている最高機関が「統合参謀本部」です。国防総省に属し大統領、国家安全保障会議および国防長官を補佐します。
我が国ではかつて太平洋戦争のさなか、大西瀧治郎海軍中将は「海軍は全力を挙げて陸軍と戦い、余力をもって米軍と戦っている」と嘆いたと言われます。陸軍と海軍のいがみ合いがいかにひどかったかを象徴しています。これでは作戦がうまく行く筈がありません。戦局が長期・複雑化してくると組織間の密接な連携が一段と必要になります。ところが「戦いに勝つため」という目的は共有しているはずですが、それが簡単ではないのです。その理由は「たこつぼ化」した組織間の主導権争いや、責任のなすり合いが生じるからです。その結果、ともすれば国益より自らの組織の利益を優先することになり、無駄な重複投資や足の引っ張り合いという事態を生じます。
これは民間企業の場合も同じです。そこで縦割り組織の弱点をカバーし、組織間の連携を強化するための横断的な組織の必要性が唱えられます。組織論としてはその通りだと思いますが、これがなかなか理屈通りには行かないのです。ここでまた主導権争いが生じるからです。うまく機能するには「トップの明確な戦略」、「横断組織のトップに就く人材」、「横断組織の必要性への意識改革」が不可欠です。私の経験からすると、横断的な組織は縦割り組織をサポートする役割として明確に位置づけるべきと考えます。対等とすると社員はどちらの指示に従うべきか戸惑うからです。
岸田内閣の下、一昨年9月、中央省庁の縦割り打破を掲げ、「デジタル庁」が発足しました。新型コロナウイルスの感染拡大への対応では、わが国の行政組織のIT化の遅れを露呈しました。我が国のDX化は喫緊の課題です。そういった観点から同庁にデジタル時代の司令塔としての役割が期待されています。ところがスタートして約2年経とうとしていますが、このところ殆ど話題に上がりません。横割り組織の難しさが分かるだけにその進捗状況が非常に気になるところです。
なお、IT化とともに民間企業組織も変革が求められます。例えば前職時代、私が自分で作成した文書をインターネットにアップロードすると、瞬時に国内・海外の社員に垂直・水平に伝わりました。ただその場合、トップの発信力が極めて重要になります。それにより以前のように、会議を重ね情報をバケツリレーのように伝達していく、多層型の組織は理論的には不要となります。そういう役割はインターネットが果たしてくれるからです。すると組織の中間にいる管理層の役割は、単に情報をそのまま伝えるのではなく、情報に対して自らの知識・経験に基づき「付加価値」を付けることが求められます。
このようにデジタル化により、トップからの現場への情報提供は極めてスピーディーかつ効率よく行えます。ところが逆に現場の声をすくい上げるのは簡単ではありません。何故なら往々にして途中で目詰まりが生じるからです。それを避けるにはやはり、「明るく、楽しく、のびのびと、風通しのよい組織」をつくることが必要です。
そして、これからの時代は、ハイテクとサイバー空間での業務の増加に伴い、「人間性尊重」が重要になります。最近は「ウエルビーイング」とか、「社員のエンゲージメント」、「パーパス経営」というような様々な専門用語が飛び交っています。要は「人間らしく生きたいなあ」という社員の気持を大切に、モチベーションを高めることが大切だということです。
追記:文科省によると、日本人留学生は2018年度は過去最高の11.5万人に達しましたが、2020年度はコロナの影響で過去最少の1500人弱まで減少しました。各種統計によると2000年から2019年の間に海外への留学生は、中国やインドが7倍、韓国も1.5倍に増加しましたが、日本は同期間に2割減少しています。文科省は5年後の2027年までに、日本人留学生をコロナ禍前の10万人規模に戻すことを目指しています。因みに1990年代における米国への学生数は日本が1位でしたが、2019年には3位に後退しています。学費の高騰が主因とされています。
一方、海外からの日本への留学生については2020年度までに30万人に増やす計画を掲げ、2019年度には過去最多の31万人に達しました。ところがコロナ禍で2020年2月から入国制限を実施したため、2021年5月現在の留学生数は24.2万人とピーク時から2割減少しています。そのうち約1割は母国からの遠隔授業でした。
若いうちに海外で学び、同世代と交流することは何ものにも代え難い財産です。たとえ借金してでも海外で学びたい若者を、官民挙げて何とか支援したいものです。