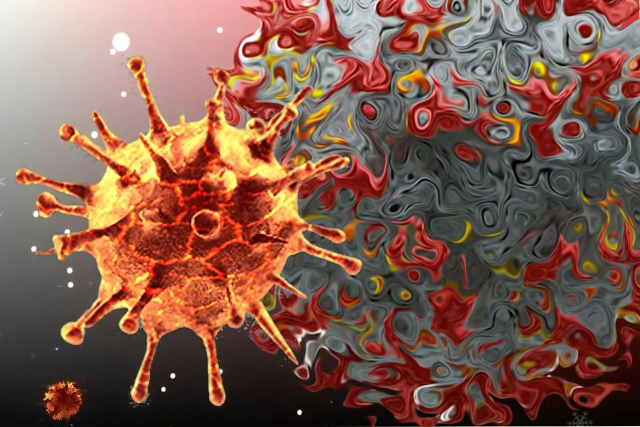最近のニュースを通じて想うこと(54)
先週に続き、最近のニュースを見聞きして想ったことについて記します。
■コロナ感染者が20万人を超える:
新型コロナウイルス感染拡大の「第7波」が猛威を振るい、1日の新規感染者数が23万人に達し、遂に世界で最多となりました。世界で最も厳しい水際対策や、国民のほぼ100%が忠実にマスク着用を励行し、ワクチンの接種率も世界水準を上回り、集会についても人数制限が実施されているにも関わらず、「なんでや」という気がします。コロナウイルスの感染が始まって以来2年半が経ち、当初は数名の感染者発生にも大きく反応していましたが、今は馴れっこになり緊張感は余り感じられません。こういったことがウイルスのつけ込む「スキ」に繋がっているのでしょう。
なお、コロナに加え、猛暑に伴う熱中症にも警戒が必要です。それにサル痘というような新たな疫病が我が国でも発生しました。これもグローバル化がもたらした副作用で、世界の果ての出来事もあっという間に足元に迫ってきます。
■ウクライナからの穀物輸出:
この「馴れ」はロシアによるウクライナ軍事侵攻についても同様です。侵攻が始まって5ヵ月が経ち、戦況は膠着状態で毎日殺戮が行われています。これについても毎日同じような映像が流れていると、特別な感情はなくなってきました。「馴れ」とは本当に恐ろしいものです。なお、軍事侵攻により止まっていたウクライナからの小麦輸出が、トルコと国連の仲介により再開される見通しが出てきました。今まで「モノ」はあるが輸送が出来ないという、サプライチェーンの目詰まりが生じていました。これによりアフリカ、中近東で数億人が餓死するリスクは緩和されそうです。
■世界経済動向:
どうやら世界は不況に向かっているようです。どの程度深刻になるかは、あまりにも不確定要素が多く予想は難しいところです。以前から世界では原油等の天然資源の高騰が見られましたが、ウクライナ問題が発生したことにより、インフレに火が付きました。その結果、日本を除き一斉に金利引き上げへ動いています。平均の利上げ率は先進国が1.7%、新興国は3%に上っています。
米国は6月の消費者物価が前月比9.1%と約40年ぶりに記録を更新したことから、7月27日、前月に続き0.75%の利上げに踏み切りました。ところが4~6月期GDPは-0.9%となり2期連続のマイナス成長となっています。景気を犠牲にしてでもインフレ抑制を優先する方針を明確にしています。一方、米国では株価も上昇していますが、これは「インフレは短期で収束する」という期待を先取りした形です。
なお、今から約40年前、当時私はニューヨークに在住していましたが、1979年のイラン革命に端を発した第二次オイルショックが米国でインフレを引き起こし、ガソリン価格が高騰した上に供給にも不安が生じたため、国中がパニックのような状態になりました。そして市中金利は信じられないかもしれませんが、1981年には20%に達したことが、今もトラウマとして記憶に残っています。今回はそこまで極端ではないと思われますが、金利の上昇に加え、中国経済の減速、グローバル化の頓挫等、景気や企業活動にマイナスに作用する要因がひしめいています。こういった外部要因は当然のことながら日本経済にも大きく影響します。
■日本の景気:
政府は2022年度の国内総生産(GDP)の実質成長率見通しを、1月時点で決めた前年度比プラス3.2%から2.0%に下方修正しました。なお、世界の主要国で金利を上げていないのは日本くらいです。まだデフレから完全に脱却しきれていないということでしょうが、消費者物価は2%を超えました。円安は物価の上昇につながります。ところが円安のメリットとして期待される訪日客の増加は、コロナの影響を受け生かしきれていません。企業業績については円安の恩恵を受けている業種もありますが、全事業者の99%を占め、就業者の7割を占める中小企業、中でもサービス産業は厳しい状況に置かれています。
≪追記≫7月28日刊行のカーゴニュースという物流業界紙に、「トラック貨物輸送事業者は自ら活路を拓け」と題して寄稿(約3400字)しました。長年トラック貨物輸送業界に関わってきた経験をもとに私見を記した次第です。トラック輸送は「くらしと経済を支えるライフライン」の役割を担っていますが、全事業者の99%が中小零細で構成され、極めて厳しい経営を迫られています。この状態を改善するには「構造改革」が必要です。近々、このブログにも掲載したいと考えています。お目通しいただき、ご意見・ご批判を賜れば幸甚です。